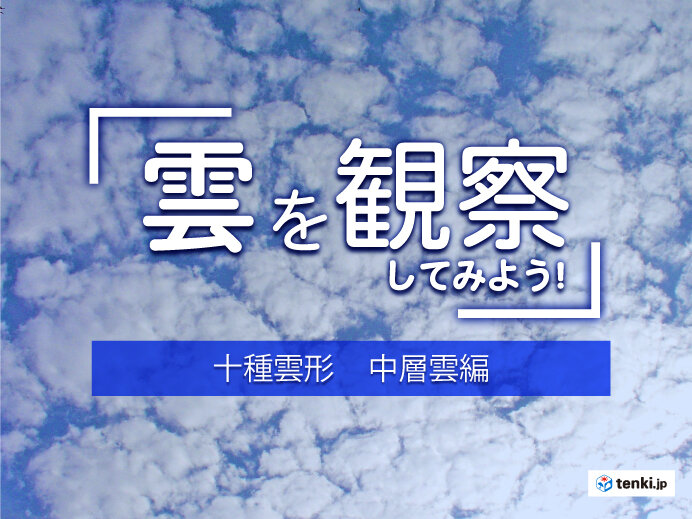雲はどうやってできる?水蒸気と気温の関係から、雲が生まれる仕組みを科学的に解説。温度低下が鍵となる理由をやさしく紹介
「空に浮かぶ雲は、どうしてできるの?」——そんな素朴な疑問の裏には、科学的にとても興味深い仕組みがあります。実は、雲の誕生には“水蒸気”と“気温の変化”が深く関係しています。地面や海から水が蒸発し、上空で温度が下がると、水蒸気が小さな水滴に変わり、やがて雲になります。本記事では、温度低下が雲を作るカギである理由や、蒸発から雲形成までの流れをわかりやすく解説します。読めば、空を見上げる楽しみが変わります。

雲はなぜできる?水蒸気と気温の基本メカニズム
雲は、空の上で「水のすがたが変わる」ことで生まれます。
わたしたちが見る白い雲は、空気の中の水蒸気(すいじょうき)が冷やされて、小さな水のつぶや氷のつぶに変わったものなんです。
地面や海から水が蒸発して空気の中に入ると、目には見えませんが、水は気体になってふわふわと空へとのぼっていきます。
その水蒸気が冷たい空気にふれると、水のつぶに戻って集まり、やがて雲ができるのです。
空気中の水蒸気とは何か?蒸発のしくみから理解
水蒸気は「水があたためられて見えない気体になったもの」です。
たとえば、やかんでお湯をわかすと「しゅーっ」と白い湯気が出ますね。
この湯気の中にも水蒸気がふくまれています。
- 🌊 海や川の水も、太陽の光であたためられると蒸発する
- ☀️ 蒸発した水は空気の中にまざり、見えなくなる
- 🌬️ 空気中にはつねに少しずつ水蒸気がふくまれている
蒸発のしくみ(イメージ)
太陽の光 ☀️ → 海や川の水 🌊 → 蒸発 💨 → 空気中に水蒸気がふくまれる
このようにして、空気の中に水蒸気がふえていきます。
気温が高いと水蒸気をたくさん含める理由とは?
あたたかい空気は「水蒸気をたくさんふくむことができる」という性質があります。
その理由は、空気があたたまると中の分子がひろがって、水蒸気が入りやすくなるからです。
たとえば、
- 夏のジメジメした日:気温が高くて、空気の中に水蒸気がたくさんふくまれる
- 冬のカラッとした日:気温が低くて、水蒸気をあまりふくめない
気温と水蒸気の関係
気温が高い → 空気がふくらむ → 水蒸気を多くふくむ ☁️
気温が低い → 空気がちぢむ → 水蒸気を少ししかふくめない 🌬️
気温が下がると飽和に達する?「飽和水蒸気量」の考え方
空気がふくめる水蒸気の量には「上限(じょうげん)」があります。
この限界を「飽和(ほうわ)」といいます。
つまり、「これ以上は水蒸気を入れられない!」という状態です。
たとえば、冷たいコップに水を入れると、外の空気の水蒸気がコップの表面で水に変わりますね。
これは、空気が冷やされて飽和になったからです。
空の上でも同じことが起きて、空気が冷えると水蒸気が水のつぶに変わり、雲ができるのです。
💡 ポイント
- 気温が下がると空気がふくめる水蒸気の量がへる
- 水蒸気があまると、水のつぶや氷になってあらわれる
- これが雲のはじまり
飽和水蒸気量のイメージ
あたたかい空気(気温高い) → 水蒸気いっぱいOK ☁️
↓
気温が下がる → 水蒸気が入りきらない → 水滴に変化 💧
↓
たくさん集まる → 雲ができる ☁️☁️
✅ ポイント
- 水蒸気は「見えない水の気体」
- あたたかい空気は水蒸気をたくさんふくむ
- 気温が下がると飽和して水のつぶができる
- そのつぶが集まって「雲」になる
蒸発から上昇気流へ:水蒸気が雲粒になるまでのプロセス
雲は「水が蒸発して空へのぼり、冷えて水のつぶに変わる」という一連の流れでできます。
この流れを「水の旅」と考えるとわかりやすいです。
水は地面や海から空へとのぼり、そこで姿を変えて雲になるんです。
地表から蒸発する水分:海・湖・陸地の役割
太陽の光が地面や水の表面をあたためると、水が少しずつ**蒸発(じょうはつ)**します。
空気の中に入りこんだこの水蒸気が、雲のもとになります。
🌊 蒸発が起こる場所の例
- 海や湖、川の水面(地球の水のほとんどがここから)
- 雨のあとの地面のぬかるみ
- 草や木の葉っぱ(植物も水を「蒸散」しています)
💡 ポイント
- 太陽の光が水をあたためて気体(水蒸気)に変える
- 水蒸気は見えないけれど、空気の中にまざっている
- 陸地や海など、いろいろな場所から空へとのぼっていく
蒸発のイメージ
太陽 ☀️ → 海 🌊・湖 🏞️・地面 🌍 → 蒸発 💨 → 空気中に水蒸気
暖かい空気が上昇する仕組み:上昇気流と気温の低下
あたたかい空気は、まわりの冷たい空気よりも軽いため、上へと動きます。
これを「上昇気流(じょうしょうきりゅう)」といいます。
上昇気流が発生すると、水蒸気をふくんだ空気もいっしょに空高く運ばれていきます。
🌬️ どうして上昇気流が起きるの?
- 太陽で地面があたたまる
- 地面の近くの空気もいっしょにあたためられる
- あたたかい空気は軽いので上にのぼる
- のぼる途中でだんだん冷たくなる(気温が下がる)
上昇気流のしくみ
太陽の光 ☀️ → 地面があたたまる 🌏 → 空気が上にのぼる ⬆️
↓
のぼる途中で温度が下がる ❄️
💡 たとえば
夏の午後に入道雲(にゅうどうぐも)がもくもく出てくるのは、地面の温度が上がり、上昇気流が強くなっているからです。
上空で冷える空気と水蒸気が雲粒に変わるステップ
空気が上へ上がるほど気温が下がります。
上空で冷えた空気は、水蒸気をたくさんふくめなくなり、余った分が**水のつぶ(雲粒:うんりゅう)**に変わります。
これが「雲ができる瞬間」です。
💧 雲粒ができるまでの流れ
- 地面から水が蒸発して空へ(→ 水蒸気になる)
- 水蒸気をふくんだ空気が上昇気流でのぼる
- 上空で冷やされ、飽和状態になる
- 水蒸気がちりやほこり(凝結核:ぎょうけつかく)にくっついて水滴に
- たくさん集まって白い雲になる
水蒸気が雲粒になるまで
🌊 海・地面 → 💨 蒸発 → 🌬️ 上昇気流 → ❄️ 冷却 → 💧 雲粒 → ☁️ 雲
💡 たとえば
冷たいコップの外に水のつぶがつくのと同じで、空の上でも冷たい空気が水蒸気を水のつぶに変えるのです。
✅ ポイント
- 水は太陽の力で蒸発し、空気の中にまざる
- あたたかい空気は上昇して気温が下がる
- 冷えた空気の中で水蒸気が水滴に変わり、雲が生まれる
気温低下がもたらす飽和と凝結:雲のできる“分岐点”
雲ができるタイミングには、「ある分かれ目(=分岐点)」があります。
それは、空気の温度が下がって、水蒸気がふくみきれなくなる瞬間です。
このとき空気の中の水蒸気が水のつぶに変わり、雲が生まれます。
気温低下=飽和水蒸気量の低下:超過するとどうなる?
空気の中には「これ以上水蒸気をふくめない!」という上限があります。
この上限のことを飽和(ほうわ)といい、そのときの量を飽和水蒸気量と呼びます。
気温が下がると、この飽和水蒸気量も少なくなります。
つまり、冷たい空気は水蒸気をあまりふくめません。
すると、空気中に入りきらなかった水蒸気が集まり、水のつぶ(=水滴)に変わります。
💡 たとえば
・冷たいジュースのコップの外に水滴がつくのも同じしくみ。
・空気が冷えて、飽和をこえてしまうと水滴があらわれます。
気温と飽和水蒸気量の関係
気温が高い → 空気がふくらむ → 水蒸気をたくさんふくめる
気温が低い → 空気がちぢむ → 水蒸気が入りきらない → 水滴ができる 💧
✅ 要点まとめ
- 気温が下がると、空気は水蒸気をあまりふくめなくなる
- 飽和をこえると、水滴ができる
- その集まりが「雲のはじまり」
凝結核(ちり・塵・エアロゾル)の存在が雲形成に重要な理由
水蒸気が水のつぶになるときには、空気中の「小さなゴミ」や「ほこり」の助けが必要です。
これを**凝結核(ぎょうけつかく)**といいます。
凝結核には、ちり・塩のつぶ・砂・けむり・エアロゾルなどがふくまれます。
水蒸気はこれらにくっつくことで、水のつぶ(雲粒)になりやすくなるのです。
💡 たとえば
・海の近くでは、波のしぶきにふくまれる塩のつぶが凝結核になります。
・都会では、車の排気ガスの中の小さな粒が凝結核の役わりをします。
凝結核のはたらき
水蒸気 💨 + ちり 🌫️ → 💧 小さな水のつぶ(雲粒) → ☁️ 雲になる
標高・前線・低気圧が気温を急激に変える場面とは?
雲ができるのは、気温が下がる場所。
では、どんなときに急に温度が下がるのでしょうか?
それには標高・前線・低気圧という3つの条件が関係しています。
🌋 1. 標高が高いところ(山の上など)
- 空気は高くのぼると気圧が下がり、いっしょに温度も下がる
- 山のてっぺんで雲ができやすいのはそのため
🌧️ 2. 前線(あたたかい空気と冷たい空気のぶつかり合い)
- あたたかい空気が冷たい空気の上にのぼると急に冷える
- このとき水蒸気が水滴に変わり、雨雲が発生
🌪️ 3. 低気圧の中心部
- 低気圧では空気が上昇する
- のぼった空気が冷えて飽和し、広い範囲で雲が発生
気温が下がる3つの場面
① 山の上 🏔️ → 標高が高く気温が低い
② 前線 ☁️ → 空気がぶつかって冷却
③ 低気圧 🌪️ → 空気が上昇して冷える
✅ 要点まとめ
- 気温が急に下がると雲ができやすい
- 山の上や前線、低気圧などが“冷却のきっかけ”になる
- これが雨や雪を生み出すもとになる
雲ができる“分岐点”とは?
- 気温が下がって空気が飽和する → 水蒸気が水滴に変わる
- その水滴が凝結核にくっついて雲粒になる
- 標高・前線・低気圧などがこの冷却をおこす
- こうして「見えない水蒸気」が「見える雲」になる
図で整理:雲のできる分岐点
気温低下 ↓
↓
飽和水蒸気量が減る
↓
水蒸気が凝結核にくっつく
↓
雲粒ができる ☁️
↓
たくさん集まると雲 ☁️☁️☁️
雲の種類と発生条件:気温・蒸発・上昇気流の関係で分類
空に浮かぶ雲には、いろいろな形があります。
それぞれの雲は「できた高さ」や「空気の動き」「気温の違い」で生まれる場所が変わるんです。
つまり、雲の形を見ると「どんな空気が動いているか」や「どんな天気になるか」もわかります。
層雲・積雲・積乱雲の違いと発生気温・蒸発条件の違い
雲は大きく分けて3つのタイプがあります。
それぞれの特徴を見てみましょう。
| 雲の種類 | 形の特徴 | 発生する高さ・気温 | 主な原因 | 天気のめやす |
|---|---|---|---|---|
| 層雲(そううん) | 空を広くおおうようなうすい雲 | 低い空(気温が低め) | 空気がゆっくり上昇して冷える | くもり・小雨 |
| 積雲(せきうん) | もくもくした白い雲(わたあめみたい) | 中くらいの高さ(昼は温かい) | 太陽で地面があたたまり、空気が上昇 | 晴れの日に多い |
| 積乱雲(せきらんうん) | どっしり大きく高い雲(入道雲) | 高い空(上空は冷たい) | 強い上昇気流とたくさんの水蒸気 | 雷雨・夕立ち |
雲の高さと種類のイメージ
高い空:積乱雲 ☁️⚡
中くらい:積雲 ☁️
低い空:層雲 ☁️☁️
💡 ポイント
- 気温が低いと、広くうすい雲(層雲)ができやすい
- 気温が高く、蒸発が盛んなときはもくもくした積雲ができやすい
- 強い上昇気流が起きると、積乱雲が発達する
冬晴れの日に「うす雲」が出る理由:気温・蒸発・凝結のコンビネーション
冬の晴れた日に、空にうすく広がる白い雲を見たことがありますか?
それは「巻層雲(けんそううん)」や「うす雲」と呼ばれる雲です。
この雲は、地上が冷たくても上空にわずかな水蒸気があるときにできます。
冷たい空気の中でも、少しの水蒸気が冷やされて氷の粒や小さな水滴になるのです。
うす雲ができるようす
冷たい空気(気温が低い) ❄️
+ 少しの水蒸気 💨
→ 小さな氷の粒 🧊 → うす雲 ☁️
💡 たとえば
- 冬の朝にうすいベールのような雲が出ているときは、上空に冷たい湿った空気がある
- 日中でも太陽の光がうすく見える日は、うす雲が太陽をおおっている
✅ 要点まとめ
- うす雲は上空の冷たい空気で水蒸気が凝結してできる
- 冬は地上の蒸発が少ないが、上空の空気が湿ると発生する
- 氷の粒が光を散らすため、空が明るく白く見える
雨を伴う雲(雨雲・雷雲)はどのように「水蒸気+気温」で成長するか?
雨を降らせる雲は、「たくさんの水蒸気」と「急な気温の低下」が合わさってできます。
これが「雨雲(あまぐも)」や「雷雲(かみなりぐも)」です。
💧 できるまでの流れ
- 太陽で地面があたたまり、水がどんどん蒸発する
- 水蒸気をふくんだ空気が上昇気流で高くのぼる
- 上空で急に冷やされ、たくさんの水滴や氷の粒ができる
- 雲の中で水滴がぶつかり合って大きくなり、重くなって落ちる(雨や雪)
- 強い上昇気流が続くと雷や大雨をもたらす積乱雲に発達
雨雲ができるまで
🌊 蒸発 ↑ → ☁️ 水蒸気をふくむ空気
→ ❄️ 上空で冷却 → 💧 水滴が集まる
→ ☔ 雨・⚡ 雷雲
💡 たとえば
- 夏の午後に急に空が暗くなって夕立ちがくるのは、地面が熱されて上昇気流が強くなったため。
- 熱帯地方ではこの仕組みで毎日のようにスコールが起きます。
✅ 要点まとめ
- 雨雲は「水蒸気+急な冷却」で発生
- 強い上昇気流があると雷雲(積乱雲)に発達
- 水滴や氷が重くなり、雨や雪として落ちる
まとめ:雲の形でわかる天気のヒント
- 広くうすい雲(層雲):おだやかな天気
- もくもく雲(積雲):晴れだけど変化に注意
- 高くそびえる雲(積乱雲):雷や雨のサイン
雲の種類と天気の関係
層雲 ☁️ → くもり・小雨
積雲 ☁️ → 晴れの合間に
積乱雲 ⚡☁️ → 雷・大雨
空の雲を観察すれば、これからの天気を少し先によむことができるんですよ。
身近な雲観察と実験:蒸発・気温・雲がつながる体験ガイド
雲は遠い空の上だけのものではありません。
実は、家の中や身近な自然の中でも「雲ができるしくみ」を体験できます。
ここでは、「蒸発」「気温の変化」「水蒸気の動き」を自分の目で確かめる方法を紹介します。
家庭でできるミニ実験:蒸発+冷却で“雲”を作ってみよう
おうちでも、ちょっとした道具で「雲ができる瞬間」を見ることができます。
これは、空の上で起きていることをミニチュアにしたような実験です。
🧪 準備するもの
- ペットボトル(500ml)
- 少しのぬるま湯(30〜40℃くらい)
- 線香のけむり(またはマッチのけむり)
- キャップ
🔬 やり方
- ペットボトルにぬるま湯を少し入れてキャップを閉める
- けむりを中に少し入れておく(※凝結核の役わり)
- 手でボトルを軽く押したり離したりして、中の空気を動かす
💨 すると……
- ボトルの中に“ふわっ”と白いもや(雲)が出てきます!
- 手を離すと空気が冷えて、気温が下がり、水蒸気が水のつぶに変化します。
家庭での雲づくり実験の流れ
ぬるま湯 → 蒸発して水蒸気が増える
↓
けむり(凝結核)に水蒸気がつく
↓
ボトルを冷やすと白い雲ができる ☁️
💡 ポイント
- けむりは雲を作る「ちり」の役わり
- 空気が冷えると飽和して水蒸気が水滴に変わる
- 温度の変化を感じながら「雲のしくみ」がわかる
山登りや飛行機で見る雲の変化:気温と蒸発の観察ポイント
山の上や飛行機の中から見る雲は、地上で見るのとはまったくちがいます。
これは「標高(たかさ)」によって気温が下がるためです。
⛰️ 山での観察
- 山を登るとだんだん空気が冷えて、雲の中に入ることがあります。
- 霧(きり)は、地上近くにできた雲と同じです。
- 雲の中では、髪や服がしっとりする=空気中に水滴がたくさんある証拠。
✈️ 飛行機からの観察
- 飛行機が雲の上を飛ぶと、下に白いじゅうたんのような雲が見えます。
- 雲の下は地上が温かく、上は冷たい空気が広がっています。
- 雲のすき間から太陽の光がさす「光のカーテン(天使のはしご)」も見られます。
山と雲の関係
地上(あたたかい) → 上昇気流 ⬆️ → 山の上(冷える) → 雲 ☁️
💡 ポイント
- 高くのぼるほど気温が下がる
- 水蒸気が冷やされて水滴になり、雲や霧ができる
- 雲の中は“空気の実験室”のような場所
雲を見ながら気温変化を読み解く:日常で使える“雲×気温”のヒント
実は、雲の形や動きを見れば「これからの天気」や「気温の変化」を予想できます。
お天気キャスターのように空を観察してみましょう。
🌤️ 雲からわかる気温の変化のヒント
- もくもくとした雲(積雲)が出てきたら → 地面があたたまり、上昇気流が強くなっている
- うすいベールのような雲(巻層雲)が広がってきたら → 上空の気温が下がり、雨の前ぶれ
- 空全体が灰色の雲(層雲)でおおわれたら → 空気が冷えて、天気がくずれるサイン
雲でわかる天気の流れ
晴れ ☀️ → うす雲 ☁️ → くもり ☁️☁️ → 雨 ☔
(気温が下がり、水蒸気がふえていく)
💡 観察のコツ
- 朝・昼・夕方で雲の形をくらべると、温度の変化がよくわかる
- 雲の高さと色で「空気の温度」や「湿度のちがい」が見えてくる
- 雲をノートにスケッチして、気温といっしょに記録すると自由研究にもピッタリ
ポイント
- 雲づくりは家でもできる(蒸発+冷却のしくみ)
- 山や飛行機から見る雲は、気温の変化を感じるチャンス
- 雲の形を観察すると、気温や天気の変化が読める
雲と気温のつながり
太陽 ☀️ → 蒸発 💨 → 上昇気流 ⬆️ → 冷却 ❄️ → 雲 ☁️ → 雨 ☔
↓
観察すれば「気温の変化」と「天気のサイン」が見えてくる!
空を見上げると、そこには「科学の教室」があります。
雲は、蒸発と気温のバランスを教えてくれる、地球のすごい観察ノートなんです。
参考元:気象庁「雲の種類」/国立科学博物館「雲のひみつ」/tenki.jp「雲のしくみ」/Photon Terrace「光と雲の関係」/小学館の図鑑NEO『空のふしぎ』ほか
まとめ
雲は、水が蒸発して空気中に含まれた水蒸気が、気温の低下によって凝結することで生まれます。気温が下がると空気が水蒸気を含む量(飽和水蒸気量)が減り、余分な水蒸気が小さな水滴や氷の粒となって集まります。これが私たちが空に見る「雲」の正体です。つまり、雲の誕生には“温度の変化”が大きく関わっているのです。